翻訳ザーゲ『ブロッケンのちっちゃな魔女』(未刊行)
本邦初訳
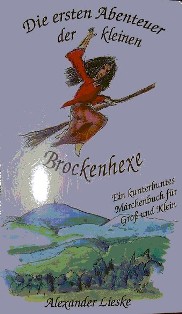
ドイツの現代児童作家アレクサンダー・リースケさんの『ブロッケンのちっちゃな魔女』は可愛い魔女のほのぼのとした物語です。
挿絵もリースケさんが描いています。超ピンボケの写真になってしまいましたが、載せました。雰囲気だけでも。
『ブロッケンのちっちゃな魔女』をザーゲのホームページで公開したい旨リースケさんにお願いしたところ、快く許可してくださいました。
リースケさんはブロッケン山のふもとの町に住んでいます。児童書以外にも作曲もしたり、絵も描いたり、いろいろな分野で活躍しています。
リースケさんのホームページはこちら。
ブロッケンのちっちゃな魔女
アレクサンダー・リースケ作 西村佑子訳
目次
1 ことのはじまり
2 新しい家づくり
3 危機一髪
4 音楽は楽しい
5 魔女資格試験
6 小さな山猫
7 新年スキー・ジャンプ大会
8 ヴァルプルギスの夜
9 新型のヒーター
1 ことのはじまり
ずいぶん昔、ハルツ(注・ドイツ中部にある山岳地帯)の森の奥に、ちっちゃな女の子が住んでいた。両親はとっくに死んでしまったので、小さな小屋にひとりっきりで暮らしていた。女の子がいつもいっしょにいる仲間といえば、森に住む動物だけだった。女の子は森の動物たちと小さいときからの知りあいだったから、いっしょにおしゃべりができたし、ぜんぜん退屈なんかしなかった。
女の子はまきから炭をどうやって作るか父親に教わっていた。父親は炭焼きだった。それで女の子は冬に凍えなくてすんだ。また母親からは森の木の実でマーマレードを作る方法や、亞麻から布を作る方法も習っていたので、きれいな服をこしらえることができた。
ただし、森には学校がなかったので、読み書きはできなかった。けれども、そんなことはどうでもよかった。女の子は森や自然のことをとてもよく知っていた。動物たちが教えてくれたのだ。
雪が深くつもった冬のある晩のこと、ちっちゃな女の子は大きな鍋の前に立って、自分と友達のウサギのためにおいしいヤマドリタケのスープを作っていた。そのとき、ドアを叩く音がした。「こんな時間にどなたでしょう」とちっちゃな女の子はたずねた。「かわいそうな旅人です。道にまよい、キノコスープのいい匂いにつられてやってきたのです」と外で返事があった。
ちっちゃな女の子がドアを開けると、かっぷくのいい男の人が立っていた。毛皮のコートには冷たい雪がつもっていた。女の子は「まあ、ではぐうぜんいらしたのですね、旅人さん」と言った。そしてお客が来たことをよろこび、中へどうぞと手まねきした。
毛皮のコートを着た男の人は肩から雪をはらいおとし、頭から大きな帽子をとり、それから暖かい台所へ入ってきた。「親切にありがとう。お嬢ちゃん。僕はハインリヒ・ハイネです」と男の人は言った。「わたしはミニーよ、こっちがお友達のウサギさん」と返事をかえし、ハイネさんの重いコートを脱がせてあげようとした。でも、男の人はことわって、自分でドアの後ろにあるコートかけにコートをかけ、その上に大きな帽子を置いた。
「まあ、本当に凍えちゃって。こんなお天気の日には厚い毛皮を着た穴熊さんだって巣から出やしないわ。暖炉の前にお坐りください。暖かいハーゲブッテのお茶をもってきます。」
ハイネさんは古くてガタビシいう安楽椅子に坐り、手を火にかざして言った。「ここに君が住んでいて、僕はなんて運がよかったのだろう。さもなきゃきっと凍え死んでましたよ。君はここにひとりで住んでいるのですか。ご両親はどこにいらっしゃるのですか。」
そこでちっちゃなミニーは自分のことを話して聞かせた。ハイネさんはとても悲しそうにして、「なんだって。君はこの深い森の中にたったひとりで住んでいて、まだ読み書きもできないんだって」と言った。「でもそんなことどうでもいいわ」とちっちゃな女の子は言った。「森にはたくさんお友達がいるし、みんな助けあっているもの。読み書きなんて必要ないわ。」
ハイネさんは眉をつりあげて言った。「ばかなことを言うんじゃない。そういうことを誰にむかって言っているんだい。僕は詩人なんだ。それに誰だって読み書きはできなきゃいけない。さもなきゃ、世の中がどうなっているかまったくわからないだろう。」
「でもわたしはこの森に住んでいて、世の中に住んでいるわけじゃないもの」とミニーは言い、キノコスープを盛った大きな皿をハイネさんに渡した。ウサギも一皿もらった。
ハイネさんは「いいかい、わかるだろう。君の住む森も世の中の一部なんだ。君はそれをまったく忘れちゃったみたいだな」と言った。そしてスープをすくって食べ、「このスープはとてもおいしい。ごちそうさま」とスープをほめた。それから少しのあいだじっと考え、そしてまたしばらくしてからこう言った。「もし君がいいなら、僕をもてなしてくれたお礼に君に読み書きを教えてあげよう。」
ちっちゃな女の子はそれも悪いことじゃないと考えてその提案に同意した。みんなの食事が終わると、ハインリヒ・ハイネさんは部屋の中をぐるりと見まわしたが、探しているものは見つからなかった。「ご両親は一冊も本をもっていなかったのかい」とびっくりしてたずねた。
「そうなの、貧乏で本が買えなかったの。でも、ウサギさんがむかし森の中の大きな石の下から一冊見つけてきてくれた。石の下に穴を掘ろうとしてね。わたし、その本を何度か見たんだけど、残念なことに読めなかった。」
それからちっちゃなミニーはたちあがって、衣装箱からとても重そうな古い本をもってきて、ハインリヒ・ハイネさんに渡した。ハイネさんはポケットからメガネをとりだし、鼻の上にかけた。そしてびっくりして大声をあげた。「なんということだ。」

「どうしたの」とミニーは興奮してたずねた。ウサギも耳をすませた。「これは魔女の魔法の本だ。もっと正確に言えば、ブロッケン(注・ハルツ地方で一番高い山。四月三十日に魔女が集まる山として有名)の魔女の魔法の本だ。」「ブロッケンの魔女の魔法の本ですって」とちっちゃなミニーがたずねた。「いったいそれ何なの。」
ハイネさんはまたも眉を高くつりあげて言った。「君は大いそぎで読み方を習うべきだと僕は思うね。ブロッケンからほんの数マイルしか離れていないところに住んでいて、ブロッケンの魔女の魔法の本が何だか君は知らないって。ブロッケンはドイツで一番美しい山だ。とても素朴な形をしている。むかし、ブロッケンには魔法のできる有名な魔女たちがいた。
僕の同僚の、尊敬すべきヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ氏はそのことについてすばらしい詩(注・ゲーテの大作『ファウスト』のこと)を書いている。だから僕も一度はブロッケンに行ってみたいと思っていた。しかし今ではもうブロッケンに魔女はいない。ひょっとしたら魔法の本をなくしてしまったのだろう。でも見たとおり、それは君のところにあったのだ。」
「魔法の本ですって」とちっちゃなミニーはびっくりした。「でもわたしがこの本で勉強してもいいのかしら。わたしはだってぜんぜん魔女じゃないもの。」
するとハインリヒ・ハイネさんは大声で笑って言った。「書かれていることは何だって学んでいい。それにどんな知識もふたつの使い方がある。ひとつはよいことに、もうひとつは悪いことに使える。そして、僕にはわかっている。君は困っている人を助けるよい人間だ。
魔女の知識をすべて知ったとしても、君なら悪い人間にならない。だから、君がこの本を読んで、いくらか魔法を使えるようになったら、君はちっちゃなよい魔女だよ。」
そしてことはこんなふうになっていった。ハインリヒ・ハイネさんは、どっちみちこんな寒い冬ではとくにすることもなかったので、森のちっちゃなミニーとウサギのところで数週間をすごし、読み書きの授業をすることにした。ミニーは熱心なよい生徒で、魔法のことならなんでも知ろうとした。実際、春になって雪解けが始まるころには、本に書いてある魔法をたくさん覚えることができた。
こうしてミニーはハインリヒ・ハイネさんに、森ですごした日々のことを思い出してもらえるように、ハルツ産のすばらしい木の杖を魔法でつくってあげることもできるようになった。ハインリヒ・ハイネさんは詩人の仕事をふたたび始めなければならなかったし、すばらしい詩を書いたり、ドイツについてじっくり考えなければならなかった。
お別れのとき、ハイネさんは言った。「さて、君が本当に読み書きを覚えたかどうか、見せてもらおう。君にシラカバの若枝でホウキを作ってあげた。空を飛ぶホウキはよい魔女のものだ。大きな魔女だろうと小さな魔女だろうと関係ない。さあ、そこで魔法の本のホウキのページをあけて、いちど試してごらん。」
ちっちゃなミニーは目次から「ホウキによる飛行」という言葉をすぐに見つけだし、きちんとそのページを開いた。そしてゆっくりと読みだした。ハイネさんがぜんぜん訂正しないことがわかると、ミニーの読み方はいっそう早く、いっそう正確になった。そして簡単とはいえない長い呪文が終わりに近づくと、ホウキがミニーのそばで舞いあがり、初めての飛行を心待ちしていた。
ハインリヒ・ハイネさんはなんとも驚いた。こうなればあとはどれも子どものお遊びと同じだ。正しい呪文をとなえたら、ただホウキにまたがって、命令をさかさに言うだけでよかった。飛びたとうと思ったら、「とべ」と言うかわりに「べと」と言う。また止まろうと思えば、単に「とまれ」の反対「れまと」と言う。
なにしろそんな具合にことは運んだ。ちっちゃな魔女は飛ぶことをうんと楽しんだ。ハインリヒ・ハイネさんは「そう、ちっちゃな良い魔女君、君は読むこともできる。風みたいに飛ぶこともできる。さて、僕は帰ろう。ところで、君はこのぶ厚い魔法の本を悪いことには使わないと約束してくれるね」と言った。
ちっちゃな女の子はうなずいて、魔法は良いことにしか使わないと約束した。こうして親切な先生は荷物をまとめて家路につくことになった。「ハイネさん、ありがとう。どうかまた来てください」とミニーは旅人であり詩人である人の背に大きな声をかけた。ウサギも手をふった。
ちっちゃなミニーは友だちみんなをブロッケン山に連れてゆき、そこに小さな葉っぱの小屋を建てた。そしてそのときからみんなは一緒に、すばらしく見晴らしのいい、でも荒涼とした山の上で暮らすことになった。こうして女の子ミニーはブロッケンのちっちゃな魔女になった。
2 新しい家づくり
ある朝、ブロッケンのちっちゃな魔女はベッドで目が覚めると身体がびしょぬれだった。そっと目をあけて、小さな葉っぱの家の屋根をじっと見た。この小屋は去年の秋に建てたものだった。
ちょうど真上の葉っぱのところに大きくふくらんだ雨粒がたれさがっていた。それもあっという間。すぐに雨粒は落ちてきて、そのままミニーの鼻にピチャとあたったので、ミニーはくしゃみをしてしまった。
ぬれたベッドから急いでとびだし、風邪をひかないように、すてきな色のバスローブに身をつつんだ。けれどもバスローブを着たとたん、もういちど「ハックション」とクシャミをしてしまった。
魔法ですばやく暖炉に細い火をつけ、お湯をわかした。熱いハーゲブッテのお茶をいれよう。お湯がわくあいだに、友だちの小スズメがドアをノックした。ミニーがドアをあけると、友だちはポタポタと鼻水を流して、悲しそうに部屋をのぞきこんだ。
「おはいり、かわいいスズメさん。すっかり凍えてしまったみたいね」と言って、すぐに戸棚からふたつめのカップをもってきた。「おいしい熱いハーゲブッテのお茶を飲みましょう。
そのあとでこの寒さをどうしたらいいかじっくり考えましょう。これじゃあどうしょうもないもの。わたしのところも雨もりがして、すっかり風邪をひいちゃった。このあいだのブロッケン山の嵐でこの小さな小屋は駄目になったんだわ」
ふたりが熱いお茶をすすっていると、またもドアをノックする音がして、ヨーロッパコマドリが入ってきて言った。「ハックション、わたしにもまだお茶いただけるかしら。外はほんとうにひどいわ」
ちっちゃな魔女はもういちど大きなやかんに水を入れた。やっとお茶が湯気をたててカップにそそがれたとおもったら、またもハリネズミと穴熊とウサギが仲間いりした。
誰もがひどく風邪をひいていた。まだ十月の末だというのに、もう嵐もきて、雪もふった。仲間全員がクシャミをし、そのうえ喉が痛くなった仲間も何人かいた。
そこでちっちゃな魔女は言った。「こんなことしていてもしょうがない。わたしたちには暖かい家が必要ね。わたしんとこの葉っぱの家は雨もりがするし、木の上の鳥さんたちもこんな天気だと、ちゃんと身を守れないんだ。でもわたしにいい考えがある」
そこにいた動物たちはクシャミするのをやめて、ちっちゃな魔女が何を言うのか緊張して聞き耳をたてた。「つまりね、みなさん、わたしたちには家が必要だってこと」
「家?家だって、どんな家だい?」とみんなは興奮してたがいに言いあった。「わたしたちにはちゃんとした家が必要なの。人間がもってるみたいな。ただしもっとうんと小さいものだけど。でもそうしたらわたしたちみんなは寒さをふせげるし、冬には凍えないわ」とミニーは言った。
ところがウサギは「でも僕は地面にちっぽけな穴を掘ることしかできない」と言った。そしてスズメも「残念ながら僕も簡単な巣を作ることしかできない」と言った。そしてミニーは「わたしは小さいし、大工道具ももってない。だから誰かに作ってもらわなければならないわ」と言った。誰もがこの提案をいいと思った。
でもハリネズミは「僕たちにはお金がない。人間は値段のはる大きな家を建てるんだ」と言った。
そこでブロッケンのちっちゃな魔女は人指し指をたてて、笑った。「ちがう、ちがう、わたしね、夏にヴォルフスハーゲンで、誰だかそこにいた男の人をよく見てたけど、その人はとっても小さな家をいくつも作ってた。おまけにとってもきれいな色だった。その人がその家をどうしたかわかるかしら」
テーブルのまわりに坐っていたみんなはううんと首をふった。「その人はね、その家を庭の木につるしたの。春になって鳥たちがそこに巣をつくることができるように。その男の人がわたしたちにも家を作ってくれるかどうかたずねてみましょうよ。すばらしい考えじゃない」
みんなはうなずいた。でもいつもお金のことを考えるハリネズミは言った。「人間がただでそんなことしてくれると思うかい。その人はきっとうんとお金をほしがるさ。僕たちにはぜんぜんお金がないじゃないか。」
でもちっちゃな魔女はねばった。「スズメさんとあたしでちょっとヴォルフスハーゲンまで飛んでいって、たずねてみるわ。それなら別にお金がかかるわけじゃないから」
それでそういうことになった。その日のうちに、ミニーはホウキに乗って、スズメといっしょにその男の人のところへ飛んでいった。空の上からでも、庭 にすてきな色の鳥小屋が見えた。
スズメはそのひとつにはいってみた。そしてとてもいい具合だと思った。でもみんなで一緒に住むには小さすぎる。それに、ハリネズミやウサギは木の上のこんなに高いところへどうやってこれるだろう。
しかし少なくともこのふたりの訪問者は運がよかった。その男の人が自動車の下にもぐって修理をしていたのだ。ふたりは彼の肩のあたりに着地した。そしてミニーが言った。
「こんにちわ、鳥小屋の大工さん。わたしはブロッケンのちっちゃな魔女です。そしてこちらが友だちのスズメです。よろしければちょっとおたずねしたいのですが」
自動車の下に頭をいれていた男の人ははい出てきた。ふたりの訪問者を見て、とてもおどろいた。「おや、おや、びっくりした。いったいどこからやって来たんだい」
「ブロッケンから直行で来ました。わたしたちは友だちといっしょにそこに住んでいるんです。でも問題がひとつあるんです。今みんな病気になってしまいました。鼻風邪とか喉の痛みとかです。
あすこの上じゃあもう冬なんです。それであなたのきれいな色のすばらしい鳥小屋をお見かけしたので、わたしたちにもそんな家をひとつ建ててくださるかどうかおたずねしたいのです」
男の人は古い自動車に寄りかかってしばらく考えてから返事をした。「よし、そうしよう。凍えてしまうなんて、いいことじゃないからな。」それから立ち上がってお客さんを家の中へ招きいれた。
男の人は大きな机の上に紙をひろげて、立派な箱から色鉛筆を何本か取りだした。「ええと、それじゃあ、そこには何人くらい住むつもりかな。」ふたりは友だちの数をかぞえて、それに客室をいくつかたした。男の人はスケッチを描きはじめた。それが終わると、ブロッケンのふたりの住人の考えをよく聞いて、色鉛筆で設計図を塗った。
「さあ、終わった。おそらく君たちの家はこんなふうになるだろう。」ちっちゃな魔女はその家がとてもすてきだと思ったけど、少し心配になった。「とてもすてきです。でもきっととても高いのでしょうね。わたしたちほんの少ししかお金がないんです。正直に言うと、まるっきりないんです」とちっちゃな魔女は悲しそうに言った。
「そうかい、でも君はちっちゃな魔女なんだろう。ちっちゃな魔女なら少しばかり魔法が使えるんじゃないの、ちがうかい」「いえ、いえ、もちろんできます。」とちっちゃな魔女は興奮して大声をあげた。「何かあなたに魔法をおかけしましょうか。そんなに大きなことでなくてもいいなら」
「ああ、それなら頼みたいことがある」と親切な男の人は言った。「ついいましがた、自動車のネジが一本壊れてしまって、そいつがすぐに必要なんだ。ひょっとして君、できるかい」
ちっちゃい魔女はこのやさしい男の人をがっかりさせないように、うんとがんばった。「シュヴップディヴップ」と呪文をとなえて、すばらしいネジを魔法で作りだした。
なんとネジの表面は金で塗られていた。ブロッケンのちっちゃな魔女はそんなにもじょうずに魔法が使えた。男の人はとても感心したようで、ちっちゃな魔女は誇らしい思いだった。
「すばらしい。ところで、君たちの友だちにも新しい家のために何かしてもらおう」と男の人は言った。「よくわかっていると思うが、ブロッケンにやってくる人々は森の中にいつもゴミをたくさん捨てていく。なにしろ人間はきちんとしていなんだ。
だから僕は提案する。家に住みたいと思うものはみんなブロッケン山をちょっとばかり掃除して、プラスティックのビンや空き缶を備えつけのゴミ箱に入れてほしい。君たちの家が出来るまでで、そのあとはいいよ。それが君たちの仕事だ」
ブロッケンのふたりの訪問客は夢中でうなずいた。男の人は二週間たったら家をブロッケンまでもっていってあげようと約束してくれた。
やったあ。スズメとミニーは、このよい報せをもって、できるだけ急いでブロッケンに飛んで帰った。そしてその日のうちに森のゴミ掃除が始まった。
十日たってほんとうに男の人はブロッケンにやってきた。腕に大きな包みをかかえていた。家はスケッチよりももっとすてきで、本当のドアや小さな窓がついていた。
住人みんなに個室があり、全員がいっしょにいられるリヴィングルームやバスタブのある快適なバスルームもあった。男の人はちっちゃな魔女のために正式な魔女の台所も作ってくれた。ちゃんと暖炉までついている。
ミニーはとても感激して、興奮のあまり、すぐに金のネジを魔法でつくりだした。鳥小屋の大工さんは喜んで「これをナイトテーブルの上に置いて、いつもブロッケンの友だちのことを思い出そう」と言った。
ブロッケンの住人は最初の雪が降るまで森のゴミ拾いをして、こんなにすばらしい新居をもらえたことに感謝した。
3 危機一髪
すばらしい夏のある日、ブロッケンでもお昼ごろにはとても暑くなっていた。ちっちゃな魔女のところにお客さんがみえた。大きなコブみたいな鼻をした小さなコーボルト(注・家の精)さんだった。いぜん、魔術会議で知り合った友だちだ。
ちっちゃな魔女は電話をもっていなかった。というのも、使いこなせるような小さな電話器がなかったからだ。それでヴィリーという名前のやさしいコーボルトさんが現れたのを見てびっくりした。
「でも君に手紙を書いたのですが、受け取っていないのですか」
「ええ、ここには郵便屋さんはいないの。シールケ(注・ブロッケン山のふもとにある小さな町)の郵便局にはずーと行ってないものですから。おそらくあなたの手紙はそこでわたしを待っているんでしょうね。でもどうやってわたしたちの家がわかったのですか」
「ウサギに会ったのです。そしたらこの山をまっすぐ上へ登っていくのだと教えてくれました。そしていま着いたところです。それにしてもハードでした。山登りは喉がかわきますね」
ちっちゃな魔女はあっというまにレモンいりミネラルウォーターのジョッキを魔法で作りだした。コーボルトは一息でほとんどぜんぶ飲みほした。
「おなかもすいているんじゃありませんか」とブロッケンのちっちゃな魔女はたずねた。
「いいえ、それよりこの近くに泳げるような湖がありませんか。お日さまがこんなにギラギラしているのですから、そうとう焼けるでしょう」
「泳ぐってのはいい考えだわ。でもここには池ひとつないんです。ブロッケンを降りたところに、水のきれいな小さな沼がひとつありますが」
小さなコーボルトのヴィリーはそこで恐ろしそうにうめいて、嘆き声をあげた。「あーあ、また下まで降りなきゃなんないとは」
「なんですって」とちっちゃな魔女は言った。「その必要なありません。わたしのローラースケートに乗ってゆけば簡単。すぐに着きます」
「でも君はどうするの」
ブロッケンのちっちゃな魔女は玄関のそばの壁にたてかけてあるホウキを指さした。「魔女がどんなことをするかわかるでしょう。魔女はもちろん飛ぶんです」
ほんとうに長くはかからなかった。ふたりは小さな沼のほとりに着いて、それから水の中でぱちゃぱちゃ楽しんだ。じゅうぶん満足したあとで、暖かいお日さまの下に寝そべった。
みごとに焼けた。でもちっちゃな魔女は日焼けどめのクリームをもっていったので、ひどい日焼けにはならなかった。
そろそろ夕方になったころ、ふたりはいっぱい泳いだのでもうれつにおなかがすいた。それで家に帰って、何かおいしいものを作ろうということになった。小さなコーボルトのヴィリーはシュヴァルツヴァルト産のおいしいハムを持ってきていた。
ちっちゃな魔女のところには水でもどしたヤマドリタケとクリがあった。それに大きなジャガイモをくわえて煮て、炒りバターのソースで味つけしよう。こんなふうに夕食のことを話しているうちに、ふたりの口には早くも生ツバがわいてきた。
でもそのとき突然ヴィリーが言った。「あーあ、またブロッケンを登らなきゃなんないのか」
ちっちゃな魔女は笑って言った。「わたしのところに来たの初めてだったわね。ハルツのことまったく知らないんだ。だってここには鉄道があって、ブロッケンの上まで行けるのよ。わたしは車掌さんをみんな知っているので、ただで乗せてもらえる。
おわかりでしょう。歩く必要なんかない。古い蒸気機関車なのよ。賭けてもいい。あなたはこれまで蒸気機関車に乗ったことなどないでしょう」
「ああ!」ヴィリーは喜び、興奮して両手をたたいた。「あたり、ほんとうに乗ったことないです。では、でかけましょうか。ブロッケン鉄道へ」
まもなくふたりはたくさんの人といっしょにシールケの駅にいた。そんなに長く待たなかった。二両編成の蒸気機関車はブロッケンにむかって走りだした。ちっちゃな魔女とヴィリーは後ろの車両のデッキに立っていた。親切な車掌さんがそこにいてもいいと言ってくれた。そこからは外の景色ががいちばんよく見えた。
お日さまはまだハルツ山地の上のほうだ。古い蒸気機関車は岩だらけのブロッケン山をあえぎながら登って行く。お日さまの光と澄んだ空気のなかで、樹木のしげる山々や丘のながめがいっそうすばらしくなる。
ふたりは上機嫌でてすりに坐り、飛ぶように走る線路の上で両足をぶらぶらさせた。ときおり蒸気機関車の汽笛が鳴り響き、ヴィリーは歓声をあげて喜んだ。
すごい急斜面にさしかかったとき、先頭の車両がとつぜんドスンとすさまじい音をたてた。そのあとすぐに後ろの車両がゆっくり、だんだんとゆっくりになった。
「いったい何だ。どうしたんだ」とヴィリーはびっくりしてたずねた。しかしちっちゃな魔女は肩をすくめるだけだった。ちっちゃな魔女にもわからなかった。それでこう言った。「ちょっと調べてみるのがいちばんね」
急いでホウキに乗ってデッキから飛びたった。そんなに遠くまで飛ぶ必要はなかった。とんだことになっていた。最後の車両が他の列車から切り離されてしまったのだ。
「あーあ、どうしよう」とブロッケンのちっちゃな魔女は考えた。困った事態になっていた。上から見ると、車輌はたちどまって、それから反対の方向に、つまり山をくだりだした。はじめはゆっくりと、そしてだんだん早く。
あわててヴィリーのところに戻り、どうなっていたか興奮しながら伝えた。ふたりは緊急ブレーキがないか探した。ほかの乗客はみんなとても興奮していて手におえなかった。誰もが通路をうろうろし、大声で「助けて、助けて」と叫んでいた。
乗客のひとりがなんとか緊急ブレーキをひいたが、とても多くの人がこの愛らしい古い鉄道に乗りたくて乗っていたので、車輌はひどく重くなっていた。最初はゆっくりだったが、それも短いあいだで、それからふたたびスピードがあがった。

「こうなったらあたしの友だちしか助けにならない」とちっちゃな魔女は興奮して叫んだ。そしてすぐさまホウキに乗って汽車の窓から外へ飛びだした。ヴィリーはひとり残されて、興奮している乗客たちといっしょにいた。みんなは恐ろしさでふるえだし、泣きだした。
ちっちゃな魔女はできるかぎり急いで森じゅうを飛びまわり、出会った鳥たちに「お願い、すぐにブロッケン鉄道まで来て。ブレーキがきかずに汽車が山をくだっている。みんな、急いでブロッケン鉄道まで来てちょうだい」と叫んだ。
この恐ろしい知らせは野火のようにすばやく広まった。どの鳥もそれぞれ出会った鳥にこの知らせを伝えたからだ。ブロッケンのちっちゃな魔女が、機関車から離されてすごい勢いで走っている車輌に戻り着くと、羽をもった小さな友だちが何百羽となくレールの上のほうでふわふわ飛びまわり、荒らあらしくさえずっていた。
「何をしたらいいんだ。何をしたらいいんだ。どうやったら助けられるんだ。こんな大きな汽車を相手にするには私たちは小さすぎる」
ブロッケンのちっちゃな魔女は鳥の大群のところまで飛んでいって叫んだ。「もちろんわたしたちは小さいけど、みんなが集まれば強いわ。みんな汽車の屋根にとまって。しっかりと爪をたててとまってちょうだい。そしてわたしの指令でいっせいに飛びたつこと。汽車の走っている方向とは反対むきに飛ぶのよ。そうすればおそらくブレーキがかかると思う」
鳥たちは言われた通りにして、屋根にしっかりととまった。どこもあいているところがないほど、たくさんの友だちがやってきた。それからブロッケンのちっちゃな魔女は指令を発した。「さあ、飛べ」
いっせいに鳥たちは羽をバタバタさせはじめた。ほんとうに汽車はゆっくりになった。
だんだんゆっくりになった。けれどもいくら小鳥たちが頑張っても汽車をとめるところまではいかなかった。小スズメが叫んだ。「僕たちだけじゃあ駄目だ。援軍がほしい。トルフハウス(注・ふもとにある場所)へ飛んでいってくれないか。ワシとタカが助けてくれるにちがいない」
はやくもちっちゃな魔女はつむじ風のような速さで飛びたち、谷を越えてトルフハウスへとむかった。そこには大きな鳥たちのすみかがある。ブロッケンのちっちゃな魔女はいつもワシには尊敬の念をいだいていた。ワシは、ちっちゃな魔女がその首にじゅうぶん坐れるほど大きいのだ。
しかし、今は緊急事態、ワシを恐れる気持ちは忘れた。運よくワシは巣にいた。そこでブロッケンのちっちゃな魔女は言った。
「ワシさん、あなたの助けが必要なんです。満員の列車がブロッケン山から猛スピードで走りおちています。わたしたちだけではとめることができません。お願いです、助けてください。でも小鳥たちになにかしたりしないでください。かれらは勇敢で、自分たちのベストをつくしているんです」
ワシは笑った。「ブロッケンの魔女だったら、ワシのすみかにはいつもけっこうな食べ物が手に入ることぐらい知っていてほしいね。もうずっと前からおまえさんのところの鳥など一羽として食べたことはない。もちろん助けてあげよう」
空の王者はこれで大丈夫。そして彼の友だちのタカはいつだってハラハラするような冒険はお手のもの。
タカさんは言った。「おいで、ブロッケンのちっちゃな魔女君。わたしの羽のあいだにお坐り。わたしはこの地でいちばん早く飛べる。それに急がなきゃならないだろう」
ほんとうを言うと、ブロッケンのちっちゃな魔女はずっと前からいちど速飛びのタカと一緒に飛んでみたいと思っていた。タカはハルツの鳥たちのなかのジェット戦闘機だ。
ともかくタカの背に乗ってブロッケンへと急いだ。列車にたどりつくと、鳥たちはみんなピーチクピーチクさえずった。「ばんざい、ばんざい」
しかし、ワシは威厳にみちて言った。「さあ、歓喜の声をあげるまえに、仕事にとりかかろう」
ワシは屋根の先端にとまった。ワシが羽を力いっぱいブルンブルンはばたけるように、鳥たちのなかでも小さいものがワシのために場所をゆずった。タカは後方の端にしっかりととまった。
それからワシは力をいれて羽をはばたかせ、ほかの鳥たちも一緒に羽をバタ バタさせた。何分かがんばったあと、ほんとうに重い車輌はとまった。
乗客のひとりが飛び下りて、車輪の前に大きな石を置いた。こうしてやっと鳥たちは屋根から離れ、近くの木に飛びうつり、休息した。だれもが力つきた。けれども、汽車や乗客を救えたことで感激もしていた。
ヴィリーの顔はまだ蒼白かったけれども、すべてがうまくいったので喜んだ。ちっちゃな魔女はちょっとのま考えて、大声で言った。「いっしょに助けてくれたみなさん、今日はわたしたちがみなさんを食事にご招待します。みなさんのために今日わたしはお料理をつくります」
友だちは歓声をあげた。そして食べ物がじゅうぶんなように、だれもが何かしら持ちよった。
祝宴は夜遅くまで続いた。ワシもタカも夜中までいた。彼らはブロッケンのちっちゃな魔女のところが気にいった。それでタカは、ちっちゃな魔女をもういちど乗せてあげると約束までした。
4 音楽は楽しい
ある日、ちっちゃな魔女はとても退屈だった。大きなひじかけ椅子に坐って、魔法の本を気のりせずにパラパラめくっていた。ちょっとしてから魔法で熱いカカオをテーブルによびだした。
しかし、カカオを飲みおわっても、あいかわらず退屈に変わりはなかった。そこで、外へ出て、少しばかりホウキに乗ってあたりを飛びまわってみようと思った。
ひょっとしたらなんかいたずらが思い浮かぶかもしれない、だれか大人にそれをしかけることもできるかもしれないと思った。けれどもちっちゃな魔女が戸口に出ると、見えるのはブロッケン山を取りかこむ濃い霧だけだった。
今日は山に登ってくる人などいないだろう。これじゃあかわいそうにブロッケンの酒場も仕事にならないだろう。大人を怒らせることもできやしない。こう考えると退屈がいっそう退屈になった。
ちっちゃな魔女は何もすることがなかったかというとそうではない。ちがう、ちがう、まともなことをする気がなかっただけだ。魔法を使わずにやらなければならないことはたくさんあったのだ。魔法は魔法の本に書いてあることしか使えない。
ブロッケンを吹きまくったこのあいだの嵐で葉っぱが山ほど、そして大きな枝が何本も小さな庭に吹きよせられて、歩くこともできない。魔女の台所には洗わなければならないものが山ほどあった。
さて彼女はホウキを手にして家の前に立ち、霧をじっと見つめた。霧はほんとうに深かったので、飛べるような状態ではなかった。それなのに、ちっちゃな魔女は退屈に腹をたてていたので、ホウキにしがみつくと灰色の霧の中へ突進していった。
まったく見通しが悪かった。それでブロッケン鉄道の線路のそばへ急いだ。ここならいい道案内になる。ただ線路について行けばいい。そしたらシールケに着ける。
おそらくそこだったらなんかあるだろう。しかしシールケにもターレ(注・ブロッケン山のふもとの町)にも、退屈なちっちゃな魔女の暇つぶしになるような面白いものなど見つからなかった。人間はみんな家や酒場にいて、おそらくちっちゃな魔女と同じように退屈しているのだろう。彼女は線路にそってさらに飛びつづけた。
もうゆうに一時間以上も空を飛んだとき、突然奇妙なもの音が聞こえた。彼女は木の上にとまり、緊張して霧のただよう静けさに耳をすませた。すると線路から少し離れたところにある古い壁のむこうから歌が聞こえてきた。楽しくて、リズミカルな音楽だ。
ちっちゃな魔女はとつぜん身ぶるいすると、ホウキにまたがって、愉快な響きの聞こえる家をめざした。その家に着いてみると、陰気な寒い天気のために窓はぜんぶ閉まっていた。ブロッケンのちっちゃな魔女は家のまわりを何回かまわってみた。それで音楽が地下室から流れてくるのがわかった。
彼女は地下室の窓に進路をとった。そして窓の格子にはりついて、地下室をのぞいた。きれいな色の照明が輝き、髪のうんと長い、かなりはでなアクセサリーをつけた若い男の人が五人、打楽器をつかって愉快な音楽を演奏していた。彼らは演奏を本当に楽しんでいるように見えた。誰もがいっぱい笑っていたからだ。
ちっちゃな魔女も笑って、身体をゆすって拍子をとった。次々と曲が演奏されて、時間は飛ぶように過ぎていった。音楽家たちが演奏や歌を終えたときには、もうすっかり暗くなっていた。
ちっちゃな魔女はもっと歌が聞けたらと思ったけれども、これはこれでじゅうぶんだった。メロディーはとても簡単できれいだったので、覚えやすかった。ちっちゃな魔女はホウキに乗って、気分よく、歌を歌いながらブロッケンの家に帰った。
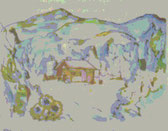
山の上の小さな魔女の家に帰りつくと、彼女はすぐにきちんとかたづけを始めた。音楽がはずみになった。さっきはどうしてあんなに気分が悪かったのだろうとじっくり考えてみたが、思い出せなかった。
ブロッケンのちっちゃな魔女は眠りこむ前に、ひまがあればいつでも、あの音楽家たちのところに飛んでいって、歌を聞こうと決心した。そしてそうした。次の週からいつも愉快な音楽家のところをたずね、歌を楽しんだ。
もうとっくに春だった。ほんとうにすばらしく晴れたある日、ちっちゃな魔女はまた音楽家のところに行ってみようと思った。この二週間ひまがなかった。しかし今日はひまをみつけたのだ。
鉄道の線路をめざし、ポツンと建っている古い音楽の壁にむかって飛んで行った。
ところが、いまちっちゃな魔女には何にも聞こえない。なんの音も聞こえない。頭がカッとして家のまわりを何回もまわった。けれども誰もいなかった。どこも鍵がかかっていて、閉まっていた。愉快な音楽家たちはいなかった。ブロッケンのちっちゃな魔女は屋根の上に飛んでいって煙突のそばに坐り、あたりを見まわした。
ひょっとしたら買い物にでかけたところなんだ、すぐに戻ってくるだろう。そう思い、二時間以上も待った。けれども音楽はまったく聞こえず、きれいな色の服を着た音楽家たちの姿も見えなかった。ちっちゃな魔女はだんだん悲しくなった。とても悲しくなった。
ちっちゃな魔女はどんなにか音楽が聞きたかったろう。最後はとても悲しくて、涙がいくすじも流れおちた。やっとホウキにまたがってそこから離れた。
かなり遠くまで飛んだとき、ちっちゃな魔女は踏切の前に自動車が何台もとまっているのを目にした。自動車は遮断機があがるのを待っているところだった。ドライバーたちは横の窓ガラスを開けて、ひじをお日さまにさらしていた。
そのとき彼女は聞いた。ブロッケンのちっちゃな魔女はカーラジオから流れるあの愉快な音楽家たちの歌を聞いた。小さな心臓がほとんどとまりそうなくらい嬉しかった。カーラジオから彼女の大好きな歌が聞こえてきた。
次の村でも自動車や家の中からあの愉快な音楽が聞こえた。ブロッケン山の上でもブロッケン酒場のスピーカーからあのメロディーが流れていた。ちっちゃな魔女はもう悲しまないでいい。
小さなラジオを買うことに決めたのだ。そうすればいつだってあの音楽家たちの歌が聞ける。
5 魔女資格試験
秋のある日、ブロッケンのちっちゃな魔女が冬用にスグリの実とブルーベリーを煮ていると、小スズメが飛んできた。シールケの郵便局からまっすぐにやってきた。くちばしにちっちゃな魔女あての手紙をくわえていた。
「なんかとても重要そう」とミニーは言って、手紙と差出人の名前をじっくり 見た。スズメは好奇心いっぱいでちっちゃな魔女を見ていた。「魔女技術監査部からだって。いったいわたしに何の用かしら」
彼女は小さなナイフをとり、封筒をきちんと開け、手紙を取りだした。とてもきれいな紙の上のほうに「国際魔女の会・魔女技術監査部」と書いてあった。
「いったいこれなんなの。わたしこんなもの聞いたことない。まあ、どんなことが書いてあるかちょっと読んでみよう」「あっ、お願い、声をだして読んでくださいな。僕は字が読めないのですから」と生まれつき好奇心の強いスズメがチュンチュン言った。
「いいわ。魔女のみなさんへ。最近、国際魔女の会に、にせものの魔法について苦情がたくさんよせられています。そこで、魔女試験、つまり魔女資格試験を実施しなければならないことになりました。
魔女は全員が魔女資格試験に参加しなければなりません。そして試験に受かった場合だけ魔法を使うことが許されることになります。すべての魔女は十一月九日にブロッケンに集まり、魔法の試験を受けなければなりません。
大きな魔女は午前中、小さな魔女は午後です。
敬具。ヨーハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ」
小スズメはあやしんで言った。「なんですって。あの有名な詩人の老ゲーテがこれを書いたというのですか。あの人はとっくに亡くなっているんじゃないですか」ちっちゃな魔女はただ頭をふってほほえんだだけだ。
「ねえ、スズメさん、あなたにも見当がつかないわね。もちろんあの方はとっくに亡くなっている。でも魔女にとってはちがうのよ。さて、ちゃんと準備するのにもう一か月しかない」
ミニーはさっそく準備にとりかかった。毎日二時間は魔法をかけて、試験勉強 をした。本をていねいに読み、道具の扱い方を学んだ。でもその日が近づくにつれ、だんだん興奮していった。老ゲーテがどんな試験を出そうとしているのかまったくわからなかったからだ。
勉強につきあっていた小スズメはちっちゃな魔女をおちつかせようとした。「どうしてそんなに神経質になるのですか。もうなんでもできるじゃないですか。どんなに難しいことだってできますよ。それにホウキに乗って飛ぶのなんか一番楽しいじゃないですか」
「ええ、それはもうできるけど、でも、あなたの耳を豚の耳にすることができない」
その通り。でもそれはスズメにはうれしいことだ。「そんなことかまいませんよ。豚の耳になって、僕に何をしろっていうんですか」
「でもゲーテおじいさんがそういうことをたずねるかもしれない。そしたらわたしにはそれができない。そしたらもう魔法を使うことができない」
「まあ、待ちましょう。三日たてばもっとわかるようになりますよ」
その三日間は早くも過ぎてしまった。ミニーにはなんのたしにもならなかった。十一月九日の前の夜はほとんど眠れず、それで翌日の朝にはすっかりくた びれていた。
けれども小スズメは濃いコーヒーを入れてやり、洋服タンスから色のきれいな服を探してやった。そのあいだちっちゃな魔女はお風呂に入ってよい香りがするようペパーミントを身体にすりこんだ。それからちっちゃな魔女は友だちのスズメにさよならして、ホウキにまたがり、ブロッケンの頂上めざして飛んでいった。
まだ頂上に着かないうちに、もう遠くから大勢の大人の魔女たちが見えた。みんなすてきに着飾っていた。何人かは革ばりの大きな机の前に列をつくって立っていた。その机のむこうには老ゲーテが背もたれのあるどっしりした椅子に坐っていた。彼はペンを手にして魔女たちの名前や住所を書きとめていた。
ミニーはそこに降りて列の最後に並び、まわりの大きな魔女たちにあいさつをした。彼女たちはたしかにみんなきれいだったけれども、かなり思いあがったふうで、そっけなくあいさつをかえした。
ブロッケンのちっちゃな魔女の番になると、老詩人は「さて、次は誰じゃな」とたずねた。ミニーはとても小さかったので、彼には見えなかった。それで、ちっちゃな魔女は急いでホウキに乗り、机の上に飛んでいって、「ブロッケンの魔女です」としっかりした声で言った。
「さあね、どちらかと言えば、ブロッケンのちっちゃな魔女と言いたいところだな」と老ゲーテ氏はにっこり笑って言った。ゲーテさんはちっちゃな魔女の 申し立てを記入し、午後四時頃のつもりでいるようにと伝えた。
試験は九時ちょうどに始まった。ほかの魔女たちは椅子に坐って試験を見ていてもよかった。最初の受験者たちがもっとも苦労した。ミニーとおなじよう に、だれもが緊張していたからだ。けれども老ゲーテはもちろんそうした精神状態のことはわかっていて、最初は簡単な課題をだした。
最初は南フランスからやってきた魔女で、ものすごくおいしい赤ワインがなみなみとそそがれたクリスタルグラスを魔法で作りださねばならなかった。それはすばらしくうまくいった。ほかの魔女たちは、自分だってそれなら同じようにうまくやれるわとつぶやいた。
そしてブロッケンのちっちゃな魔女も「わたしだってできたわ」とひそかに思った。ただし彼女にはどんな赤ワインがよくて、どんな赤ワインが悪いのかよくわからなかったけれども。彼女はこうして自分が最初の候補者でなかったことをうれしく思った。
二番目の魔女は、遠いキューバから大西洋を渡ってきたのだが、ワインにあった太い葉巻と金のライターを魔法で出さねばならなかった。これはたいして問題もなくいった。
しかし、さあ、老ゲーテが椅子にゆったりと坐りなおしたあとでは、もっと難しくなった。
イタリアからきた美人の魔女はお日さまの光を呼びださなければならなかった。列の中をざわざわという声が走った。
というのは、これはそもそも魔法の中でもっとも労力のいる魔法だった。それでもこれはいい考えだとだれもが認めざるをえなかった。ちょうどクシャミが出始めたところだったからだ。
豪華な衣装を着たイタリアの魔女はいっしょうけんめい努力した。けれどもクシャミがやんだだけだった。そして雲も少しきれたが、お日さまは姿を見せなかった。もちろん老ゲーテはどうこう言わなかった。この課題がブロッケン山の上では難しいと知っていたからだ。
そこでゲーテ氏はギリシャの魔女を呼びよせた。魔女がふたりがかりで、なんとかかろうじて机の後ろに坐っている試験官にお日さまの光があたるようにした。ただしほかの人たちまでは無理だった。
こんなことがしばらく続いた。ちょっとのあいだブロッケンにエッフェル塔が立ったりした。昼休みのあとも大きな魔女がまだ四人並んでいた。魔法の術はたいていがうまくいった。
しかし、どの課題もミニーにはとても難しすぎたので、ずっとピリピリしていた。ちっちゃな魔女はちっちゃな魔法しかかけられないということを枢密顧 問官ゲーテはわかっているはずだと、ただそれだけをひたすら頼みにした。あとでわかったことだが、ゲーテはたしかにわかっていた。
次はスイスアルプス地方の小さい魔女の番だった。枢密顧問官はまず彼女にいま何時か教えてもらいたいと言った。これは魔女たちにとってそう簡単なことではない。魔女は時計を身につけてはいけないことになっていたからだ。
グリンデルヴァルト近くからやってきたアルプスの魔女は緊張して考えこみ、魔法の呪文を唱えると、三時二十四分という時刻が思いうかんだ。老ゲーテは懐中時計を見て、よろしいとうなずいた。
それからまた次の課題になった。枢密顧問官の頭についている青緑色のリボンを群青赤にかえよというのだ。しかし、あーあ、リボンはただの真っ黒になってしまった。
スイスアルプスの小さい魔女はいっきょに神経質になってしまった。そしてリボンは黄色になってしまい、群青赤にはならなかった。ブロッケンのちっちゃな魔女はこのもうひとりの小さな魔女の目に絶望の色がうかんだのを見て、とても低い声で正しい呪文を唱えた。すると、見よ、リボンは群青赤になった。
次の課題もそんなに簡単ではなかった。いっぱい書きものをしたので、インクがなくなってしまったから、スイスアルプスの小さい魔女に新しいインクを作ってもらいたいというのだ。しかし小さな魔女は興奮してインク瓶にレモネードを呼び出してしまった。
老ゲーテがペン先にインクをつけて試したら、紙にはただ黄色の線だけがついた。そこでブロッケンのちっちゃな魔女はあらたにおせっかいをやいて、紙の上のレモネードを本当の青いインクに変えた。
老枢密顧問官はちょっと顔をしかめて言った。「これはどうも正しいやりかたとは思えん。が、まあいいだろう。いずれにせよ魔女資格試験なのだ。それにインクはインクだ。大目にみよう」
こうしてうろたえてしまったかわいそうなスイスアルプスの魔女は救われ、免許証をもらった。
「さて、ブロッケンの小さな魔女、君の番だ。ここは君の地元だから、もう少し難しい課題をだしてもいいだろう。わしの仲間だったシラーの巻き毛を二三本呼びだしてくれないか」
ブロッケンのちっちゃな魔女はほっとした。これはとても簡単だったからだ。彼女はだってケーキがとても好きだった。で彼女は呪文を唱えた。いち、に、さん、机の上にとってもすてきな生クリームいりパイ(注・生クリームいりパイとシラーの巻き毛という言葉は同音異義語)のいっぱいのった盆がでてきた。枢密顧問官ゲーテは眉を高くつりあげた。
「ああ、うまく伝わらなかったな。わしは詩人仲間のフリードリヒ・シラーの巻き毛のつもりだったのだ。しかし、君がケーキ作りの達人なら、それでもいい。それでは豚の耳(注・料理の名前)はどうだろう。わしはそのほうが好きだ」
ちっちゃな魔女はこれならうまくいったと思ったのに、いまは動揺してしまい、どうしていいのかまったくわからなくなって、小豚の貯金箱をよびだしてしまった。「おや、まあ、だが、それでもよかろう」とゲーテは言った。
「それでは別な問題をだそう。わかっているだろうが、わしはものを読むのが好きだ。で、先週の月曜日のシュピーゲル(注・鏡という名前の週刊誌)がほしい」
ちっちゃな魔女はまったく混乱してしまい、いったい鏡を使ってどうやって読むのだろうと考えこんでしまった。けれども枢密顧問官はとても賢い人だから、おそらく鏡文字で読むのだろうと思った。それできれいな銀の縁飾りのある鏡をよびだした。
しかし、またも枢密顧問官は眉をひきつらせて言った。「まあいい、このくらいにしておこう」
「でもゲーテ枢密顧問官さん、わたしはいったい何をまちがえたのですか」
「なになに、ブロッケンのちっちゃな魔女よ。君は何もまちがったことはしていない。君の魔法はとてもじょうずだ。ただ少し教養を身につけてほしいのだよ。すくなくともゴスラー紙(注・ハルツ地方の町で発刊されている新聞)くらいは読むといい。とても役にたつだろう。わしが鏡と言ったのはそういう名前の雑誌だったのだ」と老ゲーテは厳しい言いかたをしたが、片目をつむってみせた。
「それでも君は心根がいい。君があのかわいそうなスイスアルプスの魔女をどうやって助けたか、わしが気がつかなかったとでも思っているのかな」
それからゲーテ氏はちょっと笑い、だがすぐに厳しい口調で話を続けた。「よろしい、わしは君に今後五年間有効の免許証をあげよう。次のときはそんなに緊張しなくていい。そうする理由なぞまったくない。君はよい魔女だよ」
老ゲーテは儀式ばってちっちゃな魔女の手をとり、免許証を渡した。「もう最悪」と心配していたちっちゃな魔女はとてもよろこんだ。それではしゃいだ拍子に、老ゲーテの耳を豚の耳にしてしまった。
「あら、ごめんなさい。とてもうれしかったので、それだけのことです。すぐにとり消します。」「そうしてもらいたいね」と老ゲーテはこのめずらしい魔法に少しびっくりして言った。
「さもなきゃ免許証についてもういちどじっくり考えなければならないところだ。あるいは少なくとも馬の耳にしてほしいものだ。そうすれば後ろの話し声が聞こえるだろう」
しかし老ゲーテは心配することもなかった。ブロッケンのちっちゃな魔女はあっというまに豚の耳をもとの耳にしたからだ。「わかったわ。自信なんか少しでいいんだ。すべてはあるがままにうまく運ぶんだ」
晩には、老ゲーテが魔法で呼びださせたものをぜんぶ使って、ごうせいな大晩餐会が行われた。食事が終わると、老詩人は最新作の詩を朗読してくれた。そして誰もが言葉で魔法をかけることができるのだと驚いた。どんな魔女よりも立派に。
ミニーはスイスアルプスの魔女と気があった。そしてふたりはこれまでの人生ではじめてよいワインを飲んでほろよいかげんになった。
ブロッケンのちっちゃな魔女は友だちのスズメに試験がうまくいったことを知らせる前に、ブロッケンのまわりを何回かまわった。この飛行はワインのせいでそんなに優雅とはいかなかったが、とても楽しかった。
6 小さな山猫
秋はそれほど長く続かなかった。空から最初のぼたん雪が降ってきた。雪は三日三晩降り続いた。ハルツは白いシーツの下に隠れ、町や村は赤や黒の斑点みたいになった。東から強い冷たい風が吹いてきたので、外出する必要のない人は誰も外へでようとは思わなかった。ただ雪かきのときだけ外へでた。
ちっちゃな魔女は家の暖炉のそばに友だちと一緒に坐っていた。秋にじゅうぶん薪を集めておいてよかったと思った。おまけに、ウサギが家の下に穴を掘ってくれて、そこには食料品がいっぱいあった。
かぶら、じゃが、小麦粉、砂糖や塩だ。そして料理をするのに急に何かほかのものが必要になったら、ブロッケンのちっちゃな魔女が魔法で作りだした。それで何の不足もなく、クリスマスのくるのを楽しみに待っていた。
みんなは自分の部屋でほかの人のためにプレゼントを作っていた。この新居ですばらしいクリスマスを祝うことになっていた。聖ニコラウスの日はとっくに終わった。ミニーはオーブンでクッキーを焼こうと思い、そのためにサフランを少しばかり魔法で呼びだした。
そのとき鳥のものすごい羽ばたきが外から聞こえてきた。ちっちゃな魔女は魔法の杖をわきに置いて、窓から外を見ると、トルフハウス(注 ブロッケン山の下にある場所)のタカが家の前に着地したところだった。
「こんなひどい天気の日になんだって私たちのところにやってきたんだろう」と首をかしげてドアを開けた。
「タカさん、こんなおっそろしい天気にいったい何があってブロッケンまでいらしたんですか」とたずねたが、そのときちっちゃな魔女はタカさんがダークグレイの包みを爪でつかんでいるのに気がついた。
「この小さな山猫を君のところに連れて行くようワシさんに言われたのだ。君ならおそらくこの山猫を元気にすることができるだろうとね。トルフハオスのわたしたちははたしかに大きな鳥だが、こういうものはよくわからないのだ」
タカはやわらかい雪の上にそれをそっと置いた。それはほんとうにまだ子どもの山猫だった。ブロッケンのちっちゃな魔女はどうしたのかしらとタカの顔をみつめた。
「事故だ」とタカは言った。「トルフハウスへ行く上の広い道だった。自動車がスリップして、車道をとびだした。母親はひかれてしまったが、この子猫はまだ生きている」
「重傷かしら」とブロッケンのちっちゃな魔女は心配そうにたずねた。「ショックを受けただけだと思うが」ちっちゃな魔女はじっくり考えてから言った。「しっかり看護してまた元気にさせます。それにわたし、猫がうんとほしかったの。ふつうの魔女はみんな猫を肩に乗せているわ。そういうことで尊敬されるの」
ワシは頭をふって浮かぬ顔をした。「それには山猫は大きすぎると思わんかね。最初はまずネズミで試したらどうだ」ブロッケンのちっちゃな魔女は笑って、やめてと手をふった。
「ネズミですって。魔女の本にはそんなこと書いてない。でもいまはこの子猫の看護だわ。雪の上にいたのでとっても冷たくなっている」
ブロッケンのちっちゃな魔女は子猫のお腹をかかえて、暖かい魔女の家に運んだ。
タカはウサギから熱いグリューワインを一杯もらって飲み、それからふたたびトルフハオスに帰っていった。
半ば凍えてしまった小さな山猫は暖炉の前の毛布に寝かされた。そしてブロッケンのちっちゃな魔女は、子猫がまだちゃんと息をしているか聞き耳をたて、大丈夫と確信してから、にんにく入りパセリ茶を大きなコップにわかし、そこにスプーン一杯の蜂蜜を入れ、それを猫の口に注いでやった。
まもなく子猫は身体をブルブルさせ、目を開けはじめた。このお茶はそんなにも強力で身体にきくのだ。
ブロッケンのちっちゃな魔女は病気のお客さんにどこか痛いところはないかしらとたずねた。しかし子猫は首をふるだけで、はげしく泣きだした。そして「ママはもういない」と言った。
それでブロッケンのちっちゃな魔女もすっかり気がめいってしまった。彼女は毛布に坐って、子猫を腕にかかえた。
「ええ、本当に恐ろしいことね。でも人生にはそんなこともあるんだわ。わたしの両親も、わたしがまだ小さいころ死んじゃった。でもわたしはいまお友だちと一緒に生活していて満足よ」
子猫はすすり泣いた。「でもわたしには友だちなんて一人もいない」「なんてこと言うの。誰があなたをここへ連れて来たのかしら。ワシさんはあの鋭い目で道端に倒れているあなたを見つけ、タカさんがあなたをここへ連れて来た。
さもなきゃあなたは凍え死んでた。そしてわたしはあなたに健康茶をわかして、あなたを暖かい火のそばに置いてあげた。ウサギはいまあなたが寝ているその毛布をもってきてくれた。
どう、もう四人も友だちがいるじゃない。それにあと二三日もすればクリスマスよ。そしたらあなたはもっとたくさんの人と知り合いになれる」
小猫はこの言葉を聞いて、少し心が静まり、すぐに眠りこんだ。このお茶は眠るのにもきくのだ。
こうしてついにクリスマスになった。おいしいビスケットやみんなのプレゼントが用意された。赤いリンゴ、マンダリン、キラキラひかる金の糸、いい匂いのレープクーヘンやロウソクを飾ったクリスマスツリーはそれはそれはすばらしかった。
魔女の家の住人はみんな緊張してプレゼント交換のときを待った。けれどもブロッケンのちっちゃな魔女がロウソクにぜんぶ火をつけ終わるまで、誰も居 間に入ることは許されなかった。みんなは、あの小猫も、緊張して廊下で待っていた。
そして、銀の鐘の澄んだ音が鳴り響き、ブロッケンのちっちゃな魔女が大声で、「幼な子キリストが来た」と言った。
スズメがドアを開け、みんなはロウソクの火のともるクリスマスツリーを見た。みんなはおごそかに部屋へ入って、「オー、もみの木よ」を歌いはじめた。小さな山猫だけは一緒に歌うことができなかった。まだこの歌を知らなかったのだ。
それから友だちはみんな大きなテーブルのまわりに坐って、クリスマス物語に耳をかたむけた。これはちっちゃな魔女が今年用にと思いついたものだった。ウサギがレンジからイチゴポンチをもってきた。みんなは大きなクリスタルグラスにそれをいっぱい入れてもらった。
ブロッケンのちっちゃな魔女は彼女の有名な手製ビスケットをテーブルの上に置いた。
まず最初にウサギがプレゼントを取りだした。「今年は小さな山猫さんにプレゼントします。山猫さんはなにもっていないので、外で凍えることがないように、マフラーを編んでみました」
みんなはそのマフラーに感心した。小猫はプレゼントをもらい、とてもびっくりした。
次はヨーロッパコマドリの番だ。そして、どう言ったらいいのだろう、今度も小猫へのプレゼントだった。専用カップだ。誰もがそれはいい思いつきだと思った。こうして事は次々にすすんでいった。
住人は誰もが小猫の使えそうなものを考えていた。小猫のほかにプレゼントをもらった人はいなかった。でも誰もプレゼントをもらえなかったことを悲しんだりしなかった。みんなは小さな山猫がとてもかわいそうだと思っていたからだ。
小猫はプレゼントの山の後ろから少しばかり恥ずかしそうにして言った。「残念ですけど、私、みなさんへのプレゼントがないんです。でも私はいつまでもみなさんの友だちでいようと思います」
テーブルのまわりでみんなは笑って、拍手をした。ブロッケンのちっちゃな魔女は「わかったわね。もう悲しまなくていいの。今日からわたしたちがあなたの家族」と言った。
小さな山猫は嬉しくて大声でミャーオと鳴いた。そして目から涙があふれた。でもそれは嬉し涙だった。それを見たみんなも力のかぎり一緒に大声で泣いた。それから誰かが笑いはじめた。そしてとつぜん全員が笑っていた。クリスマスのお祝いは次の日の早朝まで続いた。
こうして、ブロッケンのちっちゃな魔女は、ほかの普通の魔女と同じように、猫をもつことができた。しかし、この小さな山猫は、ふつうの魔女の場合のように肩に乗ることはできなかった。
それにはブロッケンのちっちゃな魔女は小さすぎたし、小さな山猫は大きすぎた。けれどもその逆ならうまくいった。
そして春になるとブロッケンのちっちゃな魔女は山猫に乗って森を散策し、二人はとても楽しんだ。だっていつも飛ぶだけじゃあ退屈だったからだ。猫はかならず魔女の肩に乗っていなければならないとどこかに書いてあったとしても、その逆だってありうるのだ。
7 新年スキージャンプ大会
毎年のことだが、新年の朝にブロッケンのちっちゃな魔女は柔らかな暖かいダウンジャケットを着て、ヴルムベルクへ飛んでいく。そこには大きなスキーのジャンプ台があり、そこで一月一日にいつもジャンプ大会が行われる。ミニーはこのスポーツが好きだった。人間がスキー板に乗って飛ぶなんて、それはなかなか面白い。
いたるところ、おいしい焼きソーセージや熱いグリューワインの匂いがし、人々はみんな上機嫌だ。ジャンパーがじょうずに飛ぶと、そのたびに観客は歓声をあげ、両手を振りまわして「ワー」と叫んだ。
今年も同じだ。ブロッケンのちっちゃな魔女は高いもみの木の上へ飛んでいった。そこならすべてがよく見えて、見物が楽しめた。
ただ、自分でスキーに乗ってジャンプ台をすべったり、ジャンプしたりできないのが悲しかった。ホウキに乗らないで飛べるのはきっとすばらしいにちがいない。でも、そうするにはミニーは小さすぎた。
それともうひとつ残念なことは焼きソーセージが食べられなかったことだ。ちっちゃな魔女はたしかに魔女だ。しかし、あのぶ厚い魔法の本には、魔法でお金をだしたり、焼きソーセージをつくりだすことは書いてない。本が書かれた当時は、こういうものはまだなかったらしい。
でも、それはそんなにたいしたことじゃなかった。オープンサンドをもってきたし、ジャンプはいつもの年と同じくすばらしかった。
ブロッケンに帰る途中、滑空の名人オオタカに出会った。オオタカもヴルムベルクのジャンプ大会を見てきたと言った。この大きな鳥も羽なしで飛ぶことに感動したのだ。そして言った。
「ねえ、ブロッケンのちっちゃな魔女君、わたしたちふたりで動物たちのため にヴルムベルク・ジャンプ大会を準備するというのはどうだろう」
「動物たちとちっちゃな魔女のためにでしょ」とちっちゃな魔女は訂正した。「もちろんちっちゃな魔女のためにもだ。飛ぶことができて、でもいつもとは違った飛びかたをしたいと思っているものすべてのための大会だ。」
「そう、とてもすばらしい考えだわ。そしてわたしたちは誰も怪我しないようにしなければ。すべるってかなり危険だと思う」賢いオオタカはうなずいた。「もちろんそうしよう。人間がウインタースポーツはもう終わりと考えて、スキー板をしまいこんだら、わたしたちだけの新年ジャンプ大会をやろう」
「ええ、三月の第一月曜日にヴルムベルクジャンプ台で。わたしがみんなに知らせる」とブロッケンのちっちゃな魔女は飛びながらオオタカに言った。
「それにわたしたちだけの焼きソーセージを作り、グリューワインの屋台も作る」
「しかし一等賞も必要だろう」とオオタカさんは助言した。ブロッケンのちっちゃな魔女の鼻にはまだおいしい焼きソーセージの匂いが残っていたので、即座に「焼きソーセージ一本」と言った。オオワシは、すでに焼きソーセージを食べたことがあるらしく、いかにもどうかなという顔をした。
「焼きソーセージ一本は少なすぎる。もっとなにか別なものがいい。わたしたちトルフハウスの大きな鳥はハルツにやってくる旅行者からしばしば焼きソーセージをもらっているんでね。すばらしい証明書を作るというのはどうだろう。たとえば、三月ヴルムベルク・ジャンプ大会ハルツ名人とかそんなものさ」
ブロッケンのちっちゃな魔女はすぐに賛成し、証明書は魔法でつくると約束した。けれどもオオタカはまたもこまかいことを言った。「スキー板がない」ブロッケンのちっちゃな魔女は言った。「大丈夫。そういうものを作ってくれる人を知ってる。わたしたちの家を作ってくれた鳥小屋の大工さんよ」
そうしてそのようになった。鳥小屋の大工さんはいろいろな大きさのスキー板をたくさん作ってくれた。オオタカはトルフハウスの大きな鳥たちに知らせた。鳥たちは証明書がほしくて、誰もが参加すると約束した。ブロッケンのちっちゃな魔女は長い横断幕にこう書いた。
優勝は焼きソーセージ・ヴルムベルクのジャンプ台で動物と魔女のスキー・ジャンプ大会
彼女はこの幕を持って、毎日一度はハルツの山を飛びまわり、動物みんなに知らせた。三月の第一月曜日の朝、三十羽以上の鳥とちっちゃな魔女が一人ヴルムベルクのジャンプ台に集まった。それぞれが自分にあった大きさのスキー板をもらった。ワシが一番大きな板で、ミソサザイが一番小さな板だった。
ジャンプ台のゴール近くに小さな山猫がグリューワインのスタンドをだした。そのそばのスタンドではウサギが焼きソーセージを売っていた。これは鳥小屋の大工さんが調達してくれた。動物が前足や爪でつかめるような特別小さな焼きソーセージだった。しかし炭焼き網のまんなかには巨大なチューリンガーソーセージが乗っていて、スキー・ジャンプ大競技の勝者を待っていた。
大選手権大会に参加できなかったり、審判員に選ばれた動物たちはゴールのまわりに立って、グリューワインを飲んでいた。ハルツはあいかわらず雪が多くて、ヴルムベルク山頂はかなり寒かったのだ。
参加者はそれぞれクジをひいて順番を決めた。最初のジャンパーは穴熊だった。穴熊は鳥でも魔女でもなかったが、競技に参加するのをやめさせることはできなかった。それでブロッケンのちっちゃな魔女は、もしなんかあったときのためにパラシュートを作ってやった。
穴熊はごうごうと音をたててジャンプ台をすべりおり、とても遠くまで飛んだ。彼はこれまでの人生でこんなことをしたことなんてなかった。動物たちはみんなとても興奮した。
次は緑アトリの番だ。しかし、アトリはスキー板にきちんとワックスをかけなかったので、ジャンプ台の終わりのあたりでゆっくりになってしまい、穴熊が飛んだように遠くに着地することはできなかった。それでもみんなは、小さな緑アトリがとても勇敢だったので、拍手喝采した。
そのあと、アオガラ、クロイツシュナーベル、クロウタドリ、キツツキそしてヨーロッパコマドリが続いた。しかし、穴熊が最初に飛んだところまで飛べたものは一人もいなかった。じょうずに、遠くまで飛べるワシやタカやオオタカでさえ、ここまで飛べば優勝という標識まで飛べなかった。つづく十二羽の鳥たちも駄目だった。
さて、ブロッケンのちっちゃな魔女の番になった。風の抵抗をできるだけ少なくするために、思いっきりスキー板の上で身をかがめ、スピードをあげた。それから身をのばし、スキー板に乗って遠くに飛んだ。とても遠くだ。ちっちゃな魔女が空を飛ぶのをみて、みんなは歓声をあげた。穴熊の飛んだ地点をしらせる目印のもっと遠くに着地した。
ブロッケンのちっちゃな魔女は腕を高くあげて、「ばんざい、ばんざい」と叫んだ。山猫がすぐにグリューワインを一杯もってきて、友だちにお祝いを言った。「ぜったい優勝だよ」ちっちゃな魔女は遠くに飛べてうれしかったが、こう言った。「けっこういけたわね。でもまだミソサザイがいる」
観衆は、巨大なジャンプ台の上に立っている小さな鳥をじっと見つめた。ミソサザイはジャンプ台へ急ぎ、そしてエイと宙に舞った。
飛んだ。飛んだ。飛んだ。飛んだ。
そしてゴールのそばにあるグリューワインのスタンドの横にそのまま着地した。みんなは興奮した。小さなミソサザイがいちばん遠くに飛んで、競技に勝ったのだ。
穴熊が最初におめでとうと言い、それからワシ、タカ、そしてオオタカが祝福した。ブロッケンのちっちゃな魔女はいい匂いの焼きソーセージを勝ちとることができなかったので、悲しかったけれども、立派な敗者だった。それで勝者におめでとうを言った。
「すばらしいジャンプだったわ。来年わたしが勝とうと思ったら、少し練習しなきゃ」
ミソサザイは言った。「ああ、ブロッケンのちっちゃな魔女さん、わかっているでしょうが、僕は焼きソーセージは好きじゃない。きれいな証明書のほうがほしいのです。この焼きソーセージはあなたにさしあげます。あなたは二番だったのですから」
ブロッケンのちっちゃな魔女はよろこんで、焼きソーセージを穴熊と分けた。誰もが満足した。そしてブロッケンのちっちゃな魔女はついにはじめてチューリンガーソーセージを食べることができた。それはとてもおいしかった。
8 ヴァルプルギスの夜
もうほとんど五月みたいなある晴れた日、ブロッケンのちっちゃな魔女はシ ールケに郵便をとりに行くことにした。
それで、空を飛んでいると、色あざやかな大きなポスターが目にはいった。ポスターなんてそう特別なものではない。この地域で催される展覧会やコンサートや売り出しなどありとあらゆるポスターがあったからだ。
でも、古い壁にはってあったそのポスターはちょっと特別だった。ポスターに は魔女が飛んでいたのだ。ブロッケンのちっちゃな魔女はさいしょとっても混乱した。
誰かが自分のことを写真に撮って、それをポスターにはったのかと思った。しかし近づいてみると、それはスケッチだった。絵の魔女は鼻が長かった。ミニーは着地して、ホウキからおり、ポスターに書いてあるものを読んだ。
・ブロッケン山の大ヴァルプルギス夜祭 四月三十日 十時より。みなさまのおこしを心よりお待ちしてます。
ちっちゃな魔女がポスターを読んでいると、小さな男の子がおんぼろ自転車に乗って、家の角を曲がってやってきた。ミニーはその子をつかまえてたずね た。
「ねえ、ねえ、これいったい何なの」とポスターを指さした。
「ヴァルプルギスの夜のことを言ってるのかい」男の子は、ヴァルプルギスの夜なら毎年四月三十日に行われるのだから、この質問に少しばかり驚いたけど、親切に答えた。
「ヘー、ヴァルプルギスの夜に魔女がみんなブロッケンへ飛んで来て、大きな祭りをするってこと知らないのかい」
ちっちゃな魔女はとてもびっくりした。だってそんなこと今まで聞いたことがなかったからだ。この日に魔女がみんなブロッケンで会うなんてことも聞いたことはなかった。それで言った。
「正直に言うと、そんなの、知らなかった。それに、このあたりにまだほか の魔女がいるなんてまったく知らなかった」
男の子は笑って、頭をふった。「魔女なんていないに決まってるさ。村の保養管理部がいろんなところからやってくる旅行者のために作っただけなんだ。みんなが魔女の扮装をして、ブロッケンやターレのヘクセンタンツプラッツ(注・魔女の踊り場という地名)で大きな焚き火を囲んで踊るのさ」
ブロッケンのちっちゃな魔女は「ヘー」としか言えなかった。男の子はひらりと自転車に飛び乗ると、猛スピードで走っていった。
ミニーは郵便を受けとったけれども、頭は二三日後に行われるという大ブロッ ケン祭りのことでいっぱいだった。家に帰ってから、ウサギとスズメにポスターのことを話して聞かせた。
「ポスターのまんなかにホウキに乗った長い鼻の魔女がいたんだよ」ウサギは「君がそこへ行くつもりなら、僕が長い鼻をはりつけてあげるよ。とっても簡単さ」と言った。
そしてスズメは「その通りだ。去年、たまたま僕はそこを通りかかったんだが、人間がみんなおそろしく長い鼻をしていたのを見たよ。君が参加したいなら、僕たちがそういう鼻を作ってあげよう」
「えっ、わたしに参加しろって」とブロッケンのちっちゃな魔女は言った。ウサギとスズメは笑った。「そうだな、君が本当の魔女みたいに見えればね」「でもわたしは本当の魔女だよ」とブロッケンのちっちゃな魔女はうんと怒って言った。「どうしてわたしが変装しなきゃいけないの」
「人間はばかなんだ。魔女は鼻が長いと思っているのさ。だからだよ。人間はどっちみち魔女なんていないと思っているのさ」とスズメが答えた。
ついにヴァルプルギスの夜がやってきた。ブロッケンのちっちゃな魔女ははでな色の服を着て、恐ろしく長い木製の鼻をつけて家の前に立っていた。ウサギとスズメは手をならして叫んだ。「すごい。長い鼻をつけると恐ろしいな。これだと旅行者の中にいてもめだたないよ」
「ねえ、さあ見に行こう」とブロッケンのちっちゃな魔女は言って、もうホウキに乗って空を飛んでいた。そんなに長く飛ぶことはなかった。ブロッケンの頂上にもうヴァルプルギスの大きな火が見えた。
近くまで飛んで行くと、人間が何百人もいた。本当に誰もがいろんな色のつぎはぎだらけの服を着て、手にはホウキをもっていた。そして長いのや曲がったのや醜い紙の鼻をつけていた。ウサギの言ったことはあたっていた。ブロッケンのちっちゃな魔女は長い木製の鼻をつけて正しく変装していてよかった。
しかし、もちろんヴァルプルギスの祭りには、ちっちゃな魔女をのぞいて、誰ひとり本当の魔女などいなかった。
旅行者やよその国の人たちは音楽隊にあわせて踊ったり、グリューワインかグロッグ酒を飲んでいた。ここの山の上では、大きな焚き火があっても、夜はかなり寒かったからだ。
ちっちゃな魔女はグロッグ酒を買うお金をもっていなかった。それで身体を温めるために、火のまわりを二三周まわることにした。
しかし何回もまわらないうちに、にせの魔女たちは、ヴァルプルギスの火の上を誰かがホウキに乗って飛んでいるのに気がついた。
あちこちから叫びがあがった。「ちょっと見て。あそこを誰かがホウキに乗って飛んでるわよ」
人々はみんな外へ出てきた。ブラスバンドが特別にファンファーレをならした。
ブロッケンのちっちゃな魔女は、じゅうぶん身体が温まったころ、下のほうのざわめきに気がついた。着地すると、みんながちっちゃな魔女をとりかこんで、にっこり笑って挨拶した。
誰もがブロッケンのちっちゃな魔女と知り合いになりたがったので、とってもたくさんの人と握手をしなければならなかった。もちろんこの女の子が火をくぐりぬけて飛んだりするたったひとりの本当のブロッケンの魔女だということなど誰ひとり気づかなかった。
さて、ちっちゃな魔女がたくさん飛んだので休もうと思っていると、オランダから来た夫婦がやって来て言った。
「私たちはアムステルダムから来たのよ。あなたがしたこととても気にいったわ。ご両親もここにいらしてるの」
ブロッケンのちっちゃな魔女は首をふって、本当のことを言った。「いいえ、もうずっと前から眠っています。」
「そうなの。じゃあ、あなたに焼きソーセージとレモネードをご馳走したいのだけど、どうかしら。」「まあ、すてき。わたしの好物だわ」
だんなさんがみんなに焼きソーセージをもってきてくれた。そして見物人のために用意してあるベンチにみんなで坐った。三人は長いこと楽しくおしゃべりした。
夫婦は、ペンションに帰る前に、ブロッケンのちっちゃな魔女がいつかアムステルダムの彼らのところに来られるように、住所を渡してくれた。
ちっちゃな魔女はとてもよろこんで、親切な招待にお礼を言った。それからもう一度アムステルダムの新しい友人たちに敬意をはらって、火の上を大きくぐるりと飛んだ。そして別れを告げた。
9 新型のヒーター
いいお天気の日、ブロッケンのちっちゃな魔女がブロッケンの沼地の上を何度もまわっていると、森のはずれに緑の服を着た男の人たちがぼんやり立っているのに気がついた。
ちっちゃな魔女は生まれつき好奇心が強かったので、急降下して人間たちの後ろの高いもみの木の上に降りた。
そこだったら何を話しているのかよく聞こえたし、どうしてそんなところにボーと立っているのかもわかった。緑の服の男の人たちは、やがてわかったことだが、ハルツの森林官だった。みんな浮かぬ顔をしていた。
一人が言った。「こんなにたくさんの木がやられているとは実に悲しい。多くの自動車やヒーター、そして工場の排気ガスが我々の森をだめにしているのだ。人間は残念ながらこんなふうになっていることを知らない。外からは被害が見えない」
別な人がうなずいて言った。「そうだ、残念ながらその通りだ。多くの人は森を歩きまわり、木を注意して見ようなんて気持ちがないのだ。みんなただ次の旅館にむかって車を走らせ、ちょっとだけ散歩して、それからおいしいものを食べる」
「そうだ」と三人目の森林官が言った。「町の人間はまわりの自然にたいしてきちんと注意せず、ただ保養とか楽しみだけをもとめている。しかし、我々はおそらくそういうことを変えられないだろうな」
それから男の人たちはもうしばらく森を歩きまわり、病んだ木々を見てまわった。
本当のところ、ブロッケンのちっちゃな魔女は森がちゃんとなっているかどうかというような立派なことをこれまで考えたこともなかった。森林官が病気のドイツトウヒやモミの木を見分けているのをそばで見ていたので、森の上を飛んでみて、わかった。
廃棄ガスによってかなり大きな被害が生じていた。ちっちゃな魔女はホウキに乗って飛べるので、まもなくハルツじゅうを飛びまわり、森の状態がよくわかった。
家に帰り、カカオのはいった大きなカップを前にして、キッチンのテーブルに坐っていると、ウサギがドアから入って来た。「木の具合が悪いって知ってた」とウサギにたずねた。
ウサギは大きな目でちっちゃな魔女を見て言った。「森をかけまわっても、何もわからないよ」
「木のてっぺんまで飛んでゆけば、もっとよくわかるんだけど。まず病気は上から始まるからね」
「そうだね。でも僕は飛ぶことができない。どうやったら僕にもわかるんだろう」
ブロッケンのちっちゃな魔女にいい考えがあった。「おいで。二人でホウキに乗って森の上をまわろう。そうすればあたしが何を言っているかよくわかるでしょう」
そうして、ふたりはホウキに乗った。ウサギはミニーにしっかりとしがみついた。そして出発した。ホウキは二人も乗せなければならなかったので、いつ もよりは少しばかりスピードがでなかった。
しかし、ウサギも排気ガスが原因で被害をうけた木々を見ることができた。地上に戻ってからウサギはたずねた。「これをくいとめるにはどうしたらいいのだろうか」
ブロッケンのちっちゃな魔女はしばらくじっと考えてから言った。「ヒーターが空に悪い空気をはきだして、その悪い空気が木をだめにするって森林官の人たちは言ってた。だからわたしたちはヒーターを新しい型のものにしましょう」
「新しい型だって。どうやって」とウサギはたずねた。「わたしにもわからない。でもわたしたちの家を作ってくれたあの人のところへちょっと行ってみよう。あの人ならよく知っているにちがいないわ」
翌日ブロッケンのちっちゃな魔女はヴォルフスハーゲンの鳥小屋の大工さんのところへ飛んでいって、新型のヒーターについてたずねた。男の人は少しびっくりした様子で言った。
「君たちの家はかなり小さい。だからエントツからでる有害物質は特別そんなに多くはない。でも君は正しい。たとえどんなに小さなことでも、人はそれぞれよいお手本をもって先陣をきるべきだ。君たちの家のヒーターは電気にしよう。それに必要な電流は自分たちで作ろう。くわしく言うと、風から作る。そうすればおまけに電灯もつく」
ブロッケンのちっちゃな魔女はぼうせんとした顔つきになった。鳥小屋の大工さんは説明してくれた。「とても簡単なんだよ。暗くなったとき明かりをつける自転車用の発電機をつけた風車さ、それを君たちに作ってあげよう。発電機が電流を作り、その電流をヒーターに利用するんだ。だいたいブロッケンではたっぷり風が吹いている。そうしたらいつでも電流が手にはいる」
「そんなに簡単なら、どうして人間は自分の家をそうしないの」とブロッケンのちっちゃな魔女はたずねた。「うーん、人間は腰が重くて、不精で、自然のことを考えたがらない。いずれにしてもたいていの人は町に住んでいて、家だけを見ていて、だめになった木なんて見ない」
「そうね、森林官の人たちもそう言ってた。でもわたしたちはもう有害物質を空にはきださずにすむのね」「その通りだ。さっそくはじめよう。ひょっとしたらよその人たちがわたしたちの手本を見て、まねしてくれるかもしれない。」「そうだったらすばらしいわね。木もよろこぶわ」
そうしてそうなった。一週間後、鳥小屋の大工さんは風車と小さなヒーターを作りあげて、それらを魔女の家にとりつけた。すべてがとてもよく動いた。風は風車をまわし、発電機は電流を作りだした。小さな家には明かりがともり、ヒーターはすばらしく暖かい。
このニュースがハルツの動物たちのところに行きわたるのに時間はかからなかった。毎日あらたに関心をよせる人たちがちっちゃな魔女の家にやって来て、風車がどう動くか知りたがった。
そしてこの年の終わりにはほとんどのハルツの住人が新しいウインド・ヒー ターにした。ブロッケンのちっちゃな魔女は自分がよいお手本の最初の人になったことをとても誇らしく思った。
おわり